日本で徐々に関心が高まっているブロックチェーン。ビットコインなど暗号資産によって、ブロックチェーンの技術は普及しましたが、それ以外の分野は未だ発展途上にあります。製造業界もブロックチェーンは普及しておらず、各企業がさまざまな活用方法を模索している段階です。しかし、ブロックチェーンは大きな可能性を秘めており、今後製造業界で新たなスタンダードが生まれることも考えられます。
このページでは、物流の合理化を実現した企業や、サプライチェーンに活用した企業など、製造業界における非金融ブロックチェーンの導入事例・ユースケースをご紹介します。
製造業界における「非金融ブロックチェーン」の活用
製造業界では、AIやIoT技術を活用した取り組みや、DXが進められています。例えば、デジタルツイン(現実世界のデータを活用し、コンピュータ上に仮想空間を再現すること)で商品開発する企業や、生産管理システムを導入し、データの可視化に取り組む企業などがあります。IoTなど技術の導入に関しては、比較的進んでいるといえます。
一方、ブロックチェーンの導入は道半ばであるのが実情です。まだ活用事例が少ないことも影響してか、様子見という段階の企業も少なくありません。しかし、海外ではサプライチェーンにおけるトレーサビリティ向上など、活用・導入に積極的な企業が目立ちます。ただ、日本でも実証実験などの取り組みが徐々に進んでおり、今後は導入する企業も増える可能性があります。
ブロックチェーンが解決する
製造業界の問題点
データの改ざん防止
製造業界では、製品の検査データを偽装したりといった不正がたびたび発生しています。ひとたび不正が発覚すると、企業の信頼を揺るがす可能性もあるため、絶対に防止しなくてはなりません。ブロックチェーンを利用することで、原材料の調達から流通経路などの情報を、改ざんできない状態で漏れなく保存することができます。
ブロックチェーンは高いレベルのセキュリティを持っているため、改ざんを防止できるのです。
ブロックチェーンではデータを改ざんしようとしても、データが入ったブロックだけではなく、その隣、またその隣のブロックといったように、チェーン上のすべてのブロックとの整合性が取れる必要があります。
実際には無数にデータが存在するため、改ざんすることは事実上不可能です。
業務関連データの連携がしやすくなる
ブロックチェーンの技術を活用すると、複数の企業間でデータの連携や共有が容易に行えるようになります。
製造業は、消費者の手元に商品が渡るまで、品質管理や在庫状況の管理、材料の受発注、製作など、多くの業者が関わります。これまでは、各業者が別々のデータを持ち、整合性をはかることができていませんでした。しかしブロックチェーンを利用することで、すべての業者がスムーズに連携された共通データにアクセスできるようになるため、情報共有も問題なくできるようになるでしょう。
高速道路での自動決済
自動車業界ではホンダやBMW、GM、フォードなど5社が集まり、高速道路での料金支払いの際に自動決済を可能にする実証実験を行っています。現在ではETCもしくは現金を利用して支払いを行っていますが、ブロックチェーン上に車両IDをはじめとした自動車情報を記録することで、決済を自動で済ませるサービスの実現を目指しているのです。
高速道路での自動決済が可能になれば、駐車料金やサービスエリアでの飲食の支払いも自動決済が可能になるかもしれません。
製造業におけるブロックチェーン活用のメリット
スマートコントラクトによるコストの削減
スマートコントラクトは、契約を自動化する仕組みです。
たとえば製造業では、製品を作るのに必要な材料が欠品することがないように、一定量まで在庫が減少したら、調達先に自動的に材料を発注する契約を行うことが可能になります。
ブロックチェーンの技術を活用することで、これまで発注に必要だった人的、金銭的コストの削減につながるでしょう。
不良品発生時のトレーサビリティ向上
ひとつの製品が工場での作成段階から消費者の手元に渡るまで、とても多くの業者が関わることが多いです。
多くの製造現場では、不良品発生箇所を特定するために、部品の受け入れ時に問題がないか確認して記録しているケースが多いでしょう。
その履歴をブロックチェーン上に残すことで、万が一問題が発生した場合にどこで問題が発生したのかをすぐ確認できるようになります。
このように、ブロックチェーンに部品情報や在庫情報、流通経路などをすべて記録していくことで、完全なデータをすべての業者で共有できるようになるのは大きなメリットといえるでしょう。
企業間でデータの連携が可能になる
ブロックチェーン技術を活用することで、企業間でのデータ連携が可能になる点も大きなメリットです。
今までは企業間でのデータ連携をする際データの整合性がとれない、連携するシステムの構築に多大なコストがかかるなど様々な問題があり、システムの連携がなかなか進んでいませんでした。
しかし、ブロックチェーンでのシステム連携を使うことでデータの同期が自動的に実施され、全ての参加者がリアルタイムで情報を保持できるようになります。
またデータの取引もブロックチェーンネットワーク上で行われるため、データ管理にかかる工数が大幅に減る点も大きなメリットです。
製造業でのブロックチェーンの活用事例
サプライチェーン全体の需給バランスの可視化
NTTデータが提供しているクラウド型情報活用プラットフォーム「iQuattro」に対して、トレーサビリティ、取引実在性証明などを実装した事例です。
ブロックチェーン技術の利用により、これまで管理負担が大きく難しかった在庫の管理単位でのトレーシングが高い信頼性と秘匿性を保ち、リアルタイムで可能になりました。
※参照元PDF:独立行政法人情報処理推進機構『非金融分野におけるブロックチェーンの活用動向調査 報告書』(https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/trend/ug65p90000001hkf-att/000079568.pdf)
製造業界の導入事例・ユースケースを掲載している
おすすめの開発会社
トレードログ

トレードログは、非金融ブロックチェーンの導入支援を行っている会社です。豊富な導入事例がありますが、製造業では、資生堂の子会社でのブロックチェーン技術導入に携わった実績があります。
資生堂の導入事例
大手化粧品製造メーカーの資生堂では、子会社のザ・ギンザが運営するスキンケアブランドにトレードログが提供するブロックチェーン導入ツール「YUBIKARI」を導入しました。これによって物流の合理化や、O2O(Offline to Online)マーケティングの一気通貫を実現しています。
例えば、製品に添付されたシールを剥がすとQRコードが現れ、読み取ると製品の登録サイトに遷移する仕組みを整えています。データはブロックチェーン上で管理され、オンラインとオフラインの購入データの一元化を実現しています。また、購入情報の統合だけでなく、偽造品防止によるブランド保護も可能としています。
トレードログの会社概要
| 会社名 | トレードログ株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋5F |
| 電話番号 | 公式サイトに記載なし |
| 業務内容 | ブロックチェーン関連事業、データ活用事業 |
| 公式URL | https://trade-log.io/ |
IBM

ソフトウェア開発やコンピュータ関連サービスを手がけるIBM。ブロックチェーンのプラットフォームも開発しており、製造業ではルノーグループがプロジェクトを立ち上げ、コンプライアンス認証に関する実証実験を行っています。
ルノーグループの導入事例
フランスの自動車メーカーであるルノーは、エクシード(eXtended Compliance End-to-End Distributed)と呼ばれるブロックチェーンプロジェクトを立ち上げました。エクシードは2019年に始まったプロジェクトで、2020年9月まで実証実験が行われました。
EUでは、2020年に自動車の市場監視を目的とした規制が施行されました。ルノーはこの規制に対応させる取り組みの一貫として、自動車部品のコンプライアンスを認証するためにエクシードを実施したとのこと。実証実験では、100万件以上の文章が保存され、1秒間に500件のトランザクション処理に成功しています。エクシードを導入することで、コンプライアンス認証をリアルタイム化し、規制が強化された場合でも応答性と効率を確保できるとしています。
IBMの会社概要
| 会社名 | 日本アイ・ビー・エム株式会社(米IBMの日本法人) |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町19-21 |
| 電話番号 | 03-6667-1111 |
| 業務内容 | コンピュータ関連サービス、ハードウェア・ソフトウェア開発など |
| 公式URL | https://www.ibm.com/jp-ja |
EY
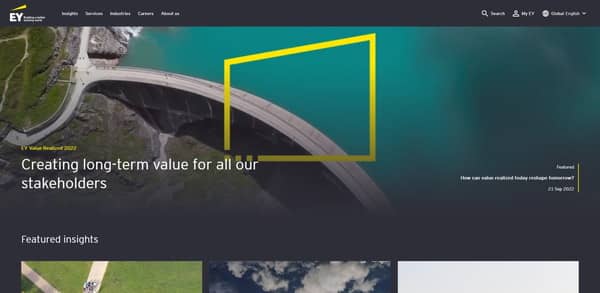
EYは、会計や税務、コンサルティングサービスなどを手がけるイギリスの会社です。ブロックチェーンの分野にも携わっており、ここではワインのトレーサビリティに活用した事例をご紹介します。
Blockchain Wineの導入事例
Blockchain Wineでは、ワインの生産から販売に至るまでのプロセスをブロックチェーンで管理し、情報の確認や追跡が可能な仕組みを構築しました。ぶどうの産地や収穫日、ワインを瓶詰めした日付などを収集し、ブロックチェーン上で管理。ワインのラベルのQRコードを読み取ることで、消費者が各情報を確認できるようにしています。なお、ブロックチェーンの情報は暗号化されるため、書き換えや偽造が困難です。
このような仕組みを整えることで、ワインの信頼性を担保できます。ワインに限らず、トレーサビリティにブロックチェーンを利用すれば、製品の信頼性を向上させることが可能です。
EYの会社概要
| 会社名 | EY Japan株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー |
| 電話番号 | 03-3503-2510(代表) |
| 業務内容 | 会計、税務、コンサルティングサービス |
| 公式URL | https://www.ey.com/ja_jp |
海外の製造業界におけるブロックチェーン活用事例
Tech Mahindra
インドのTech Mahindraは2021年に、ブロックチェーン開発企業StaTwigと提携し、「VaccineLedger(ワクチンレジャー)」を導入しました。
メーカーから医療機関にワクチンが流通する過程で起こり得る期限切れや偽造、在庫切れなどを、ブロックチェーンの技術を使って監視できるため、過剰在庫を抱える心配もなくなりました。

